子どもが全然ごはんを食べてくれない。好きなものばかり要求して、栄養のバランスなんてとても考えられない…。
毎日頑張って作っても、ほとんど手をつけられないと、親の心も折れそうになりますよね。
でも、その“偏食”には、実はちゃんと理由があるんです。
この記事では、子どもが偏食になる原因や、家庭でできる対応法、そして少し気が楽になる考え方をご紹介します。
子どもの「食べない」理由を理解しよう
「なんでうちの子はこんなに食べないの?」と悩む親御さんは多いものです。
でも、実は子どもたちには「ちゃんと理由」があることがほとんど。
まずは子どもの立場に立って、偏食の背景を知ることから始めてみましょう。
● 味覚が敏感すぎる
子どもの舌は、大人よりもずっと繊細。
特に苦味・酸味などを強く感じやすく、ピーマンやほうれん草、トマトなどを「苦い」「酸っぱい」と本能的に避けてしまうのです。
「子どもはみんな甘いものが好き」と言われるのは、こうした味覚の敏感さによるものなんですね。
● 食感や見た目の拒否反応
ぬるぬるしたオクラ、ドロッとしたなす、ブロッコリーのモサモサ感…。
子どもにとっては「なんだか気持ち悪い」「怖い」と感じることもあります。
また、色や形が「見慣れない」「変わってる」だけで、警戒心が働くのも自然な反応です。
● 過去の「まずかった」体験
一度「吐きそうになった」「無理やり食べさせられた」などのネガティブな経験があると、子どもはその食材を「もう絶対に食べたくない」と記憶してしまいます。
たとえ調理法を変えても、「あれはイヤだった」という記憶が先に立ってしまうことも。
● 親のプレッシャーが逆効果になることも
「ちゃんと食べなさい!」「残さないで!」という声かけ、つい言ってしまいますよね。
でも、それが子どもにとっては「食事=怒られる時間」になってしまうことも。
食卓が“戦場”のようになってしまうと、さらに食べることへの拒否感が強まってしまいます。
我が家のリアル体験
偏食は、誰にでも起こりうること――それは頭では分かっていても、いざ我が子が全然食べてくれないと、本当にしんどいですよね。
ここでは、我が家で実際に起きた“偏食エピソード”と、その中で試してみた工夫をご紹介します。どれも小さなことばかりですが、確かに変化のきっかけになりました。
● トマトを一切受け付けなかった長男
うちの長男は、2歳の頃からトマトが大の苦手でした。
給食でも残してしまうし、家庭でも口に入れることすら拒否。丸い形も、ジュルッとした食感も、見ただけで「イヤ!」と目をそむける日々…。
最初は「一口だけでも」と必死に説得していましたが、逆効果でした。
● 一緒に“育てて”みたら、変化が!
そんな中、たまたま始めたベランダ菜園が転機になりました。
「お水あげてみる?」「芽が出たね!」と、長男と一緒にミニトマトを育てていたある日、
赤くなった実を自分で収穫した彼が、突然「食べてみようかな」と口にしたのです。
最初は一口だけ。でもその顔は、ちょっと得意げで嬉しそう。
それからというもの、完全克服とまではいかないものの、「トマトはちょっとだけ食べる」というポジションになりました。
● 小さな成功体験の積み重ねがカギ!
この出来事で学んだのは、子どもは「自分で決めたこと」なら案外挑戦してみるということ。
そして、「食べられた!」という体験が、次のチャレンジへの自信につながるということです。
偏食克服は一朝一夕にはいきませんが、小さな一歩が必ず次につながっていきます。
子どもが“成功体験”を重ねられるよう、環境や声かけを工夫することが大切なんだなと感じました。
やさしい偏食対策
「ちゃんと食べさせなきゃ」「栄養が足りないかも」――そう思えば思うほど、気持ちが焦ってしまうものですよね。
でも、偏食は“戦うもの”ではなく、“寄り添うもの”。
この章では、実際に効果があった工夫や、専門家のアドバイスに基づいた「やさしい偏食対策」ご紹介します。
完璧を目指さず、できるところから少しずつで大丈夫です。
無理に食べさせない
「一口でも食べて!」と無理に口に入れさせるのは、逆効果になることが多いです。
子どもにとっては“嫌な記憶”になり、ますます食べたくなくなってしまうことも。
「今日は見てるだけでOKだよ」「匂いだけ嗅いでみる?」など、“食べない自由”も尊重してみましょう。
調理法・切り方・盛りつけを変えてみる
同じ食材でも、形や食感が違うだけで食べてくれることがあります。
例:
- 生のきゅうりは苦手 → 塩もみで柔らかくするとOK
- トマトは切ると嫌がる → 丸ごとのミニトマトなら食べる
- ピーマンは炒めると苦手 → 細かく刻んでカレーに混ぜれば食べる
子どもは視覚的にも敏感なので、カラフルな盛りつけや顔に見立てたお弁当風アレンジも効果的です。
一緒に料理や買い物をする
「自分で選んだ」「自分で作った」ものには、子どもは興味を持ちやすいです。
買い物で「今日は何を入れようか?」と聞いてみたり、料理中に簡単なお手伝いをお願いしたりするだけでもOK。
食べることに“主体性”が加わることで、苦手意識が薄れていくことがあります。

家庭菜園や観察活動もおすすめ
たまたま始めたベランダ菜園が転機になりました。
「お水あげてみる?」「芽が出たね!」と、長男と一緒にミニトマトを育てていたある日、
赤くなった実を自分で収穫した彼が、突然「食べてみようかな」と口にしたのです。
最初は一口だけ。でもその顔は、ちょっと得意げで嬉しそう。
それからというもの、完全克服とまではいかないものの、「トマトはちょっとだけ食べる」というポジションになりました。
食卓の雰囲気を「楽しい時間」に
食事中は、叱らない・急かさない・比べないことが基本です。
つい「弟は全部食べたよ?」「早くしなさい!」と言いたくなるけれど、子どもにとってはプレッシャー。
「今日は○○が好きだったんだね!」「スプーンの持ち方、上手になったね」など、食べたこと・やったことを認めてあげる声かけに変えると、雰囲気がガラッと変わります。
まとめ
この出来事で学んだのは、子どもは「自分で決めたこと」なら案外挑戦してみるということ。
そして、「食べられた!」という体験が、次のチャレンジへの自信につながるということです。
偏食克服は一朝一夕にはいきませんが、小さな一歩が必ず次につながっていきます。
子どもが“成功体験”を重ねられるよう、環境や声かけを工夫することが大切なんだなと感じました。


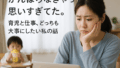
コメント